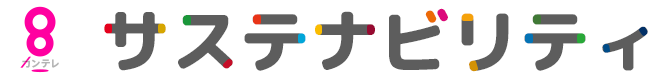尼崎市立小田北中学校
尼崎市立小田北中学校

はじまる
みる
授業の題材は、大阪湾のゴミを取材した『newsランナー』の特集「汚されるラピュタの島」で、目標番号は11番「住み続けられるまちづくりを」と14番「海の豊かさを守ろう」です。
生徒の皆さんは事前にこの特集をみて、感想や質問を講師に送り授業を受けます。
題材

講師
しる
最初に本中カメラマンは、実際に取材で使っている、ENGカメラ、水中カメラ、ドローンなどを操作してその機能や撮影方法を紹介し、代表の生徒さんにもカメラをかついでもらって操作方法などを体験してもらいました。