2008年9月15日(月)
自立への絆 ~地域療育の現場から~
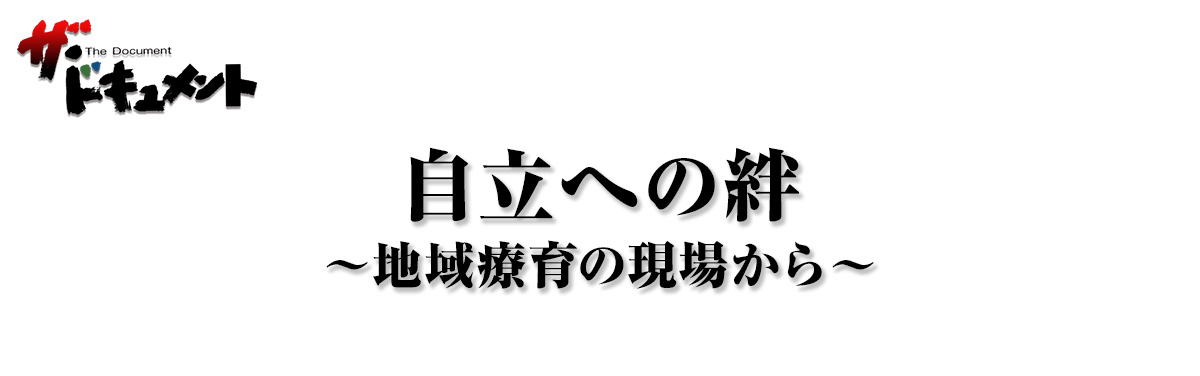
語り
豊田康雄(関西テレビ放送)
企画意図
平成17年の「発達障害者支援法」、18年の「障害者自立支援法」、19年には「特別支援教育を推進する学校教育法の施行」…。障害児・障害者を取り巻く環境がここ数年で激変している。これまでの療育を支えていた自治体の福祉予算は頭打ちとなり、「病院から在宅へ」の時代の流れが加速した。支援の現場は金も人も火の車。医療的ケアが必要でも、医師が不足している。家族による介護にも限界がある。
障害児支援は、「施設から地域へ」の舵は切られたが、「地域で障害児が自立する」ための明確な処方箋は、法律や行政からは見えてこない。その上、障害者と家族にとって、お互いの事情はそれぞれ異なる。一致しているのは、障害児を育てる親と本人たちの、自立への懸命の模索だ。番組では、さまざまな障害児の親子の家庭・療育現場を通して、「地域での自立」には何が必要かを考える。
障害児支援は、「施設から地域へ」の舵は切られたが、「地域で障害児が自立する」ための明確な処方箋は、法律や行政からは見えてこない。その上、障害者と家族にとって、お互いの事情はそれぞれ異なる。一致しているのは、障害児を育てる親と本人たちの、自立への懸命の模索だ。番組では、さまざまな障害児の親子の家庭・療育現場を通して、「地域での自立」には何が必要かを考える。
番組内容
「兵庫県立のじぎく療育センター(神戸市西区)」。今年3月、50年の歴史に幕を閉じた。「医療・福祉・教育」の3つが併設され、30年前は、理想的療育環境の施設と言われた。その頃は最新の医療技術を求め、220のベッドは満床状態だった。しかしその後、医師不足や赤字財政などさまざまな要因で、廃止となった。ここに通っていた700人は、バラバラになった。「医療的ケアも必要な障害児の施設をつくる」という当初の説明は反故にされ、医師不足もあって、リハビリ病棟さえオープンできていない。
由良典子さんは、「のじぎく療育センター」で歯科衛生士として働いていた。障害児をもつお母さんたちに「障害児の母だから仕事できないはおかしい。自立しましょう」と声をかけてた。息子の中学3年の泰輔さんは筋ジストロフィー。筋ジストロフィーは筋力が落ち体が硬直する難病。限られた時間、出来るだけ泰輔さんと一緒に居たいと思うので、仕事は短時間だけにして家族との時間を大事にしている。その時間を預かってくれる施設のデイサービスに頼るのだが、体調が悪い時は、吸引など医療的ケアが必要で、受け入れてくれる施設が極端に減る。同じように「のじぎく」に子供が通っていた家族会副代表の平山真由美さんとともに、療育施設「ルネス花北(姫路市)」を見学にいく。そこで出会った宮田所長のある言葉から、自分たちの将来の有るべき姿が少しずつ見えてくる。
この「ルネス花北」に通う障害児の3つ子(6歳)がいる。姫路市に住む萩原さん一家。2歳から5歳の間、外来保育で障害児の子育てを伝授された。学んだことはリハビリの方法や抱き方などのノウハウだ。それはすなわち、「子どもをどのように自立させるか考える親の姿勢を作る」ことだった。3人で障害が一番重い、レナさんは就学にあたって、他の兄弟とともに「普通小学校へ行く」と譲らない。両親や「ルネス」の職員は、レナさんの強い意思をサポートする。この地域では、公立小学校に進学するためには、「就学指導」という壁がある。「加配」の先生のための予算繰りが、教育行政では先行してしまうのだ。6歳児3人兄妹はこの壁に向かってゆく。
由良典子さんは、「のじぎく療育センター」で歯科衛生士として働いていた。障害児をもつお母さんたちに「障害児の母だから仕事できないはおかしい。自立しましょう」と声をかけてた。息子の中学3年の泰輔さんは筋ジストロフィー。筋ジストロフィーは筋力が落ち体が硬直する難病。限られた時間、出来るだけ泰輔さんと一緒に居たいと思うので、仕事は短時間だけにして家族との時間を大事にしている。その時間を預かってくれる施設のデイサービスに頼るのだが、体調が悪い時は、吸引など医療的ケアが必要で、受け入れてくれる施設が極端に減る。同じように「のじぎく」に子供が通っていた家族会副代表の平山真由美さんとともに、療育施設「ルネス花北(姫路市)」を見学にいく。そこで出会った宮田所長のある言葉から、自分たちの将来の有るべき姿が少しずつ見えてくる。
この「ルネス花北」に通う障害児の3つ子(6歳)がいる。姫路市に住む萩原さん一家。2歳から5歳の間、外来保育で障害児の子育てを伝授された。学んだことはリハビリの方法や抱き方などのノウハウだ。それはすなわち、「子どもをどのように自立させるか考える親の姿勢を作る」ことだった。3人で障害が一番重い、レナさんは就学にあたって、他の兄弟とともに「普通小学校へ行く」と譲らない。両親や「ルネス」の職員は、レナさんの強い意思をサポートする。この地域では、公立小学校に進学するためには、「就学指導」という壁がある。「加配」の先生のための予算繰りが、教育行政では先行してしまうのだ。6歳児3人兄妹はこの壁に向かってゆく。
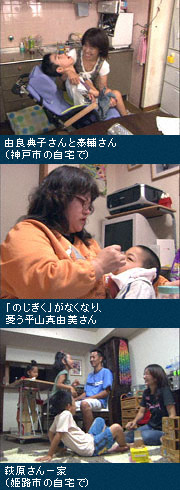
スタッフ
ディレクター:塩川恵造
撮影:松本比呂之
編集:中島福夫
撮影:松本比呂之
編集:中島福夫


