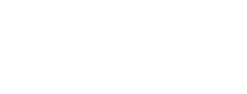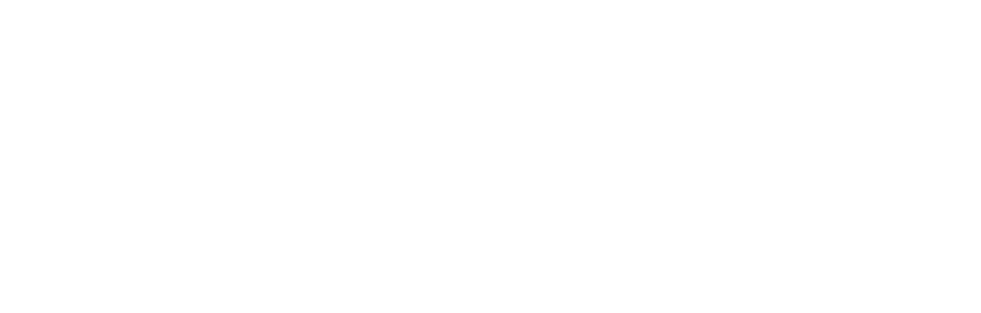“弁護士 兼 記者”のディレクターが追う「刑事司法」の世界
11月17日“弁護士 兼 記者”のディレクターが追う「刑事司法」の世界
なぜ福崎さんのことがずっと気になってしまうのか。
今回の取材は自分の過去と向き合い続けることにもなった。
私が日本の刑事裁判に絶望したきっかけがある。
2007年に周防正行監督の「それでもボクはやってない」を観た時だ。
痴漢冤罪事件を題材に、日本の刑事司法の問題点が見事なまでに凝縮された映画で、弁護士を目指していた私は“現実”を突きつけられた。
今回の取材は自分の過去と向き合い続けることにもなった。
私が日本の刑事裁判に絶望したきっかけがある。
2007年に周防正行監督の「それでもボクはやってない」を観た時だ。
痴漢冤罪事件を題材に、日本の刑事司法の問題点が見事なまでに凝縮された映画で、弁護士を目指していた私は“現実”を突きつけられた。

映画の公開から16年、裁判員制度が始まるなど大きな動きもあったが、圧倒的な有罪率の高さや“人質司法”と呼ばれる身柄拘束の問題など、大事な点はあまり変わっていないように思える。
なかでも根本的な問題は、日本の刑事裁判が“有罪推定”で動いているのではないかということだ。
刑事裁判の基本中の基本だといえる「疑わしきは罰せず」の原則が、実際の裁判では「疑わしきは罰する」になっているのではないかという疑問が私の中でいつまでも拭えずにいる。
なかでも根本的な問題は、日本の刑事裁判が“有罪推定”で動いているのではないかということだ。
刑事裁判の基本中の基本だといえる「疑わしきは罰せず」の原則が、実際の裁判では「疑わしきは罰する」になっているのではないかという疑問が私の中でいつまでも拭えずにいる。

記者2年目の時だった。公判を傍聴し続け、無罪を確信していたある事件。判決の当日、無罪判決が言い渡される想定でニュース原稿も準備し、傍聴席の一番前に座った。しかし、裁判長から言い渡されたのは、まさかの有罪判決だった。

判決理由を聞いていて、裁判官が有罪にしようか無罪にしようか迷っていて、無罪の確信を持てないから有罪にしたというふうにしか感じられなかった。やっぱり、刑事裁判は”有罪推定”だったのか…。裁判所を後にして、有罪のニュース原稿を書かなければならなかった時の絶望的な気持ちは今も忘れられない。

その後も、刑事裁判の現状に絶望する気持ちと、どこかで絶望しきれない気持ちが行ったり来たりしながら、取材を続けている。そんな時、いつも頭をよぎるのが福崎さんのことだった。彼の真意は何だったのか。その真意の先に、日本の刑事裁判を考える大きなヒントが隠されているように思えてならなかった。