2014年9月14日(日)深夜1:35~2:30
復興住宅 高齢者の反乱 ~震災20年目の現実~
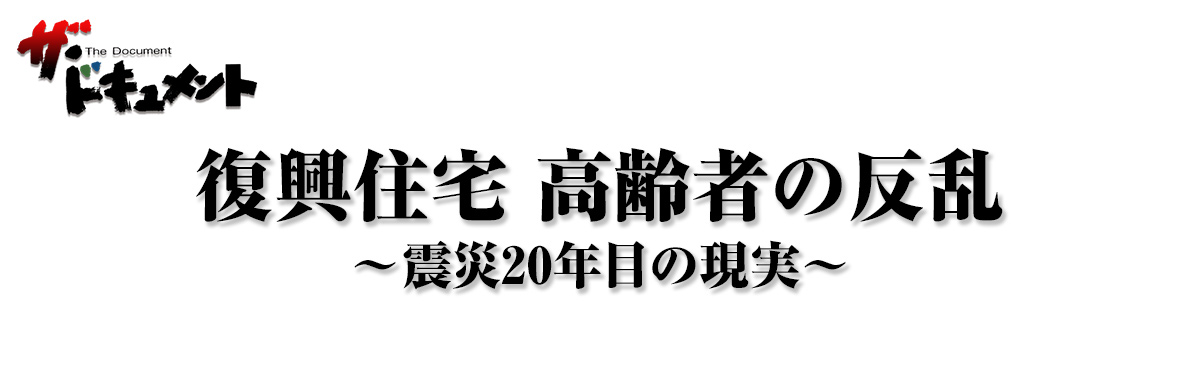
番組内容
来年で阪神淡路大震災から20年になります。街は復興を遂げたように見え、震災の傷跡を探すのは難しく感じます。しかし、目を凝らしてみると、震災を引きずって生きている人たちがいます。20年目の被災を生きる人たちを、復興住宅で取材しました。
集合住宅入居者の高齢化は、復興住宅だけの問題ではありません。ただ、復興住宅は震災後の政策の結果、高齢化が早く進んだため、前例のない課題に直面しています。いわば、日本の未来のひとつが復興住宅にあります。
復興住宅は、大震災の後、住む場所を失った被災者のために作られた公営住宅です。震災後、避難所と仮設住宅で数年を過ごした被災者にとって、復興住宅はようやく落ち着ける我が家でした。復興住宅の使命は、自宅再建が難しい生活力の弱い人に家を提供することなので、高齢者が多く集まりました。震災から20年、被災当時60歳だった人は80歳になろうとしています。兵庫県の今年1月の発表では、復興住宅の65歳以上の高齢化率は約5割に達し、一般県営住宅の3割を大きく上回っています。入居者の高齢化が大きな問題です。
神戸市長田区の復興住宅・県営西尻池高層住宅は、戸数116戸のうち大半が高齢者専用の「シルバーハウジング」仕様のため、特に高齢化が進んでいます。住民の平均年齢は77歳(名義人平均)で、「姨捨山マンション」だと自嘲気味に呼ぶ入居者もいます。
この夏、自治会の解散話が持ち上がりました。自治会役員が持病の悪化で退任を申し出たものの、後継者はなく自治会の維持が困難になったのです。
集合住宅入居者の高齢化は、復興住宅だけの問題ではありません。ただ、復興住宅は震災後の政策の結果、高齢化が早く進んだため、前例のない課題に直面しています。いわば、日本の未来のひとつが復興住宅にあります。
復興住宅は、大震災の後、住む場所を失った被災者のために作られた公営住宅です。震災後、避難所と仮設住宅で数年を過ごした被災者にとって、復興住宅はようやく落ち着ける我が家でした。復興住宅の使命は、自宅再建が難しい生活力の弱い人に家を提供することなので、高齢者が多く集まりました。震災から20年、被災当時60歳だった人は80歳になろうとしています。兵庫県の今年1月の発表では、復興住宅の65歳以上の高齢化率は約5割に達し、一般県営住宅の3割を大きく上回っています。入居者の高齢化が大きな問題です。
神戸市長田区の復興住宅・県営西尻池高層住宅は、戸数116戸のうち大半が高齢者専用の「シルバーハウジング」仕様のため、特に高齢化が進んでいます。住民の平均年齢は77歳(名義人平均)で、「姨捨山マンション」だと自嘲気味に呼ぶ入居者もいます。
この夏、自治会の解散話が持ち上がりました。自治会役員が持病の悪化で退任を申し出たものの、後継者はなく自治会の維持が困難になったのです。

番組では、自治会の副会長(後に体調不良で退任)・寺田孝さん(75)の日常を中心に、高齢化から崩壊寸前の自治会活動や、人生の最終盤を復興住宅で過ごす高齢者の皆さんを取材しました。

自治会は県に相談したものの、県は「自治会を維持してほしい」の一点張り。共益費を管理している自治会がなくなればエレベーターの電気代の支払いさえ滞りかねません。防火責任者や、修繕を要する個所についての県への連絡業務など、多くの役割を担っているため自治会の解散は一大事です。
しかし、役員が高齢化し日常の事務が難しいのも事実です。かつて復興住宅では、震災を生き延びた者同士という連帯感から住民交流会なども盛んに行われました。しかし入居者が歳をとるにつれて活力は低下しています。そんな厳しい状況が自治会問題に表れたのです。
県に冷たく押し戻され、解決策も見いだせない自治会は、どのような道をたどることになるのでしょう…
しかし、役員が高齢化し日常の事務が難しいのも事実です。かつて復興住宅では、震災を生き延びた者同士という連帯感から住民交流会なども盛んに行われました。しかし入居者が歳をとるにつれて活力は低下しています。そんな厳しい状況が自治会問題に表れたのです。
県に冷たく押し戻され、解決策も見いだせない自治会は、どのような道をたどることになるのでしょう…


被災地の今から、日本の未来の課題が見えてくるドキュメンタリー番組です。
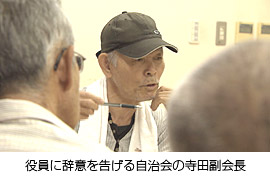

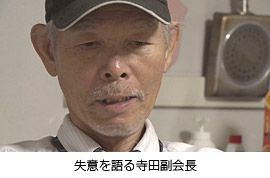

ディレクター:豊島学恵(関西テレビ報道番組部)
プロデューサー:兼井孝之(関西テレビ報道番組部)
プロデューサー:兼井孝之(関西テレビ報道番組部)


