2009年4月29日(水)午後 3:58~4:53
父の国 母の国 —ある残留孤児の66年—
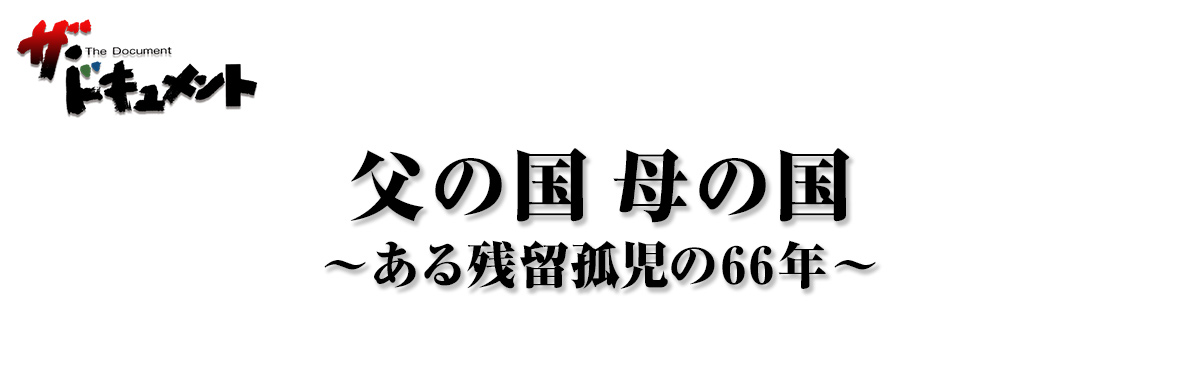
受賞
ギャラクシー賞奨励賞
文化庁芸術祭 テレビドキュメンタリー・優秀賞
坂田記念ジャーナリズム賞 第2部門
ヒューストン国際映画祭プラチナ賞
文化庁芸術祭 テレビドキュメンタリー・優秀賞
坂田記念ジャーナリズム賞 第2部門
ヒューストン国際映画祭プラチナ賞
語り
優香
企画意図
終戦前後、中国東北部に残され、肉親とも生き別れながら、かろうじて生きながらえた「中国残留孤児」。孤児らが「国の支援策が不十分」として訴えた集団訴訟を経て、去年4月からようやく「改正中国残留邦人支援法」に基づく支援策がスタートした。
しかし、この支援策で本当の幸せを見出せるようになったのだろうか。
支援策後の生活を取材し、社会がどう帰国者たちに向き合うべきか、考え直したい。
しかし、この支援策で本当の幸せを見出せるようになったのだろうか。
支援策後の生活を取材し、社会がどう帰国者たちに向き合うべきか、考え直したい。
番組内容
中国残留孤児の兵庫訴訟で原告団長を務めた初田三雄(はつたみつお)さん、66歳。初田さんの人生は、「生命の危機」と「貧困」の連続だった。終戦時は2歳。もちろん当時の記憶はない。旧満州の奉天、現在の瀋陽で中国人に育てられたが、1960年代後半から始まった「文化大革命」では、日本人だという理由で迫害を受け、1972年の日中国交回復後も農村などを転々と移転した。祖国・日本への思いは強まった。
しかし、残留孤児が本格的に帰国できるようになったのは、9年後の1981年。多くの孤児が、中年になってからだった。政府は日本語の不自由な人々に十分な支援をせず、7割もの孤児が生活保護のもと、厳しい制約をうけながらその後生活している。
しかし、残留孤児が本格的に帰国できるようになったのは、9年後の1981年。多くの孤児が、中年になってからだった。政府は日本語の不自由な人々に十分な支援をせず、7割もの孤児が生活保護のもと、厳しい制約をうけながらその後生活している。

初田さんは、44歳になって日本に帰国。その後、肉体労働を続けたが60歳でその仕事も定年となり、定年直後の収入は厚生年金の月五万円のみだった。「働けるうちは自立したい」と、アルミ缶を拾って兵庫県伊丹市の県営住宅で妻と生活している。孤児たちはこうした帰国後の苦しみを、裁判に訴えた。
全国15か所で裁判が行われたが、神戸地裁だけは「明確な国の責任」を認め、国による新しい政策をスタートさせる原動力になった。
新しい支援策は、全国の原告・弁護団が裁判の取り下げと引き換えに受け入れたもので、明るいニュースのはずだったが、初田さんは納得がいかない。それは、この制度が「社会保障」という位置づけのため、「生活保護」をベースにしていて、全員が平等に受けられるものではなく、制約も多かったからだ。
全国15か所で裁判が行われたが、神戸地裁だけは「明確な国の責任」を認め、国による新しい政策をスタートさせる原動力になった。
新しい支援策は、全国の原告・弁護団が裁判の取り下げと引き換えに受け入れたもので、明るいニュースのはずだったが、初田さんは納得がいかない。それは、この制度が「社会保障」という位置づけのため、「生活保護」をベースにしていて、全員が平等に受けられるものではなく、制約も多かったからだ。

多くの残留孤児は、国の責任が認められないままであることには不満を抱きながらも、支援策を受けて生きることを選択したが、初田さんは「給付金」の申請を拒否して、まだアルミ缶を拾い続けている。
なぜ、初田さんはそこまでこだわるのか…。
初田さんの人生を知るため、今年3月、中国・瀋陽に同行した。そこで取材班が目にしたのは、養母の墓参りすら出来なかった初田さんの深い心の傷だった。墓に向かって初田さんは語りかける。
「お母さん、あなたは私に怒るでしょう、愚かものだと。しかし息子は今になってわかった。一番大事なのは誇りを持って生きること。恥ずかしくない生き方をすること…」
そして小さなお墓にしがみつき「小さい墓を見て申し訳なく思う」と号泣した…。
政治的には「解決した」残留孤児問題ではあるが、改めて私たちがこの問題をどう考えて、どのように帰国者に向き合うべきかを考えたい。
なぜ、初田さんはそこまでこだわるのか…。
初田さんの人生を知るため、今年3月、中国・瀋陽に同行した。そこで取材班が目にしたのは、養母の墓参りすら出来なかった初田さんの深い心の傷だった。墓に向かって初田さんは語りかける。
「お母さん、あなたは私に怒るでしょう、愚かものだと。しかし息子は今になってわかった。一番大事なのは誇りを持って生きること。恥ずかしくない生き方をすること…」
そして小さなお墓にしがみつき「小さい墓を見て申し訳なく思う」と号泣した…。
政治的には「解決した」残留孤児問題ではあるが、改めて私たちがこの問題をどう考えて、どのように帰国者に向き合うべきかを考えたい。
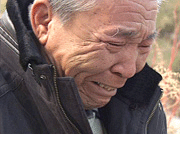
スタッフ
プロデューサー:土井聡夫(関西テレビ)
ディレクター:柴谷真理子(関西テレビ)
撮影:吉川浩也(コールツプロ)
編集:野上隆司(関西テレビ)
MA:山岡正明(東通AVセンター)
効果:萩原隆之(テレコープ)
素材協力:フジテレビジョン 他
ディレクター:柴谷真理子(関西テレビ)
撮影:吉川浩也(コールツプロ)
編集:野上隆司(関西テレビ)
MA:山岡正明(東通AVセンター)
効果:萩原隆之(テレコープ)
素材協力:フジテレビジョン 他
ディレクターから一言
ディレクター 柴谷真理子
中国残留邦人のための「新しい支援策」は、驚くほど人によって評価が違います。
取材していると、どう評価すればよいのか混乱します。弁護団にも、「あれで最善」「社会情勢を考えれば妥当」と評価する人がいる一方で、この結果に悔やみ、苦しんでいる人もいます。「残留孤児」の中にも「生活が良くなった」と感謝する人もいれば、「尊厳が回復されていない」と声を荒げる人もいます。「政治的な解決」の結果は、こういうものだろうか?と考えさせられます。
私は、「制約のある支援策」となった背景が、「国民の理解が得られないから」ということには、違和感を覚えています。「理解」といっても、国民のほとんどは、「国が残留孤児に何をしてきたか」を知らないと思います。こうした背景には、我々メディアにも責任の一端があるのではないかと感じています。
これまで「支援策」については、喜びの声が報道されてきましたが、今も心の傷の癒えない「孤児」がいることを、番組を通じ伝えられたら…と思います。
取材していると、どう評価すればよいのか混乱します。弁護団にも、「あれで最善」「社会情勢を考えれば妥当」と評価する人がいる一方で、この結果に悔やみ、苦しんでいる人もいます。「残留孤児」の中にも「生活が良くなった」と感謝する人もいれば、「尊厳が回復されていない」と声を荒げる人もいます。「政治的な解決」の結果は、こういうものだろうか?と考えさせられます。
私は、「制約のある支援策」となった背景が、「国民の理解が得られないから」ということには、違和感を覚えています。「理解」といっても、国民のほとんどは、「国が残留孤児に何をしてきたか」を知らないと思います。こうした背景には、我々メディアにも責任の一端があるのではないかと感じています。
これまで「支援策」については、喜びの声が報道されてきましたが、今も心の傷の癒えない「孤児」がいることを、番組を通じ伝えられたら…と思います。


